かつて原爆資料館に展示されていた「被爆再現人形」。多くの人たちに強い印象を与えてきましたが、いまは展示されていません。
この人形の調査・研究を続けている美術作家がいます。人形は、原爆の悲惨さをどのように伝えてきたのでしょうか。作家の思いを取材しました。
◇ ◇ ◇

写真を拡大
原爆でやけどを負い、両手を前に突き出して逃げまどう姿ー。髪は焼け、服には血がにじみ、爪の先から皮膚が垂れ下がっています。
かつて原爆資料館に展示されていた女性と女学生、そして少年の「被爆再現人形」をとらえた、実物大の写真です。

現代アート作家 菅 亮平さん(広島市立大学 芸術学部 講師)
「私自身も愛媛県出身なので、小学6年生の修学旅行で、この人形を実際に見ています。非常に怖かった印象があります。この人形のことだけはよく覚えています」
制作したのは、現代アートの作家で広島市立大学講師の菅 亮平さん(41)。人形の構造や素材などを調査し、3月に開いた個展で発表しました。

東京芸術大学の大学院を修了し、アートを通して原爆の歴史や悲惨さをどう伝えるか模索していた菅さん。関心を持ったのが、いまも多くの人の記憶に残る「被爆再現人形」でした。
菅 亮平さん
「私たちはどうやって歴史を継承していくのか、『被爆再現人形』が一体何であったのか。この人形は何を伝えて、あるいは何を伝えられなかったのか。その問題を改めて考えたいということが、私の今回の取り組みの出発にあります」


「被爆再現人形」の歴史は長く、原爆資料館に最初に展示されたのは、50年以上前の1973年。等身大の蝋人形で、ガラスケースに入っていました。

1991年にはプラスチック製にかわりました。ガラスケースはなくなり、被爆直後の燃えさかる街を歩く3体の人形は、来館者に強い印象を残しました。
来館者(2013年当時)
「怖い」「やっぱり一番怖い…」

しかし、遺品などの「実物」を重視するよう展示を見直すことになると、人形を外す方針が示されました。
原爆資料館 志賀賢治 館長(2013年当時)
「『実物』が伝える迫力は相当なものがあると、私どもは確信しています」
ただ、「来館者がイメージしやすい」「恐ろしさが伝わる」などと、人形を残すべきだという意見もあがりました。

街の人(2013年当時)
「これを見て戦争の悲惨さを感じていた」
「自分たちはこれを見て育った。今後の人にもこれを見て育ってほしい」
賛否の意見が分かれる中、人形は展示から消えました。

菅さんは、いまは資料館の収蔵庫に眠る3体を2024年5月から8か月間借り受け、文化財の保存修復に関わる専門家とともに調査を始めました。
もう一度、「人形論争」を起こすつもりはありません。ただ “作りもの” が持つ「力」や「危うさ」を明らかにするためにも、人形を忘れてはいけないと考えています。


菅 亮平さん
「昨年5月に私が保管庫の扉を開けるまで7年間、誰の目にも触れていない状況ではありました。もしかしたらそのまま風化したかもしれない。人形が風化する前に、人形の役割について考える状況をつくりたかった」
人形のX線透過写真です。
鉄の台座と棒で固定され、肩や腰はボルトで止めてあることが分かります。
精巧なガラスの義眼で作られた目は、本物のように見えます。

白い背景の高精細カメラで撮影した写真は、原爆資料館では見えなかった細部まで分かります。
垂れ下がった皮膚に、人毛とみられる髪の毛。
女学生の名札には「村山」と書かれていました。
菅 亮平さん
「燃えさかる炎、地面が燃えている設定なので、下から光を強い光を当てて…」

原爆資料館で展示されていた当時のライティングを再現した写真では、そこに人がいるかのような臨場感が生まれます。
菅 亮平さん
「原爆被害の事実を矮小化させて理解させてしまうという“リスク”がある一方で、ぱっと見て、原子爆弾というものが落ちると街は、人はこうなるということが、“イメージ”として突きつけられる」


「被爆再現人形」に強い思いを持ち続ける被爆者がいます。
98歳の阿部静子さん。18歳で被爆し、顔や右半身に大やけどを負いました。あの日、人形と同じように、がれきの街を逃げました。
被爆者 阿部静子さん(98)
「皆さん、人形と同じように逃げよう逃げようとして一生懸命でした。私もその中の1人でした。こちらから先の皮膚がずるっと剥けて。爪のところから垂れ下がっておりました」

証言活動を続けてきた阿部さんは、まず人形を見てもらうことで、子どもたちの理解が深まったと話します。
被爆者 阿部静子さん(98)
「人形で想像できますから。皆さん傷の痛みを訴えたり、うめき声を発したり。人形では血の臭いも何もしておりませんが、想像して人形を元にして想像して聞いてくださいという風に証言を進めておりました」

そして今も、原爆の悲惨さを生々しくイメージできる人形の展示復活を望んでいます。
被爆者 阿部静子さん(98)
「『被爆再現人形』も生ぬるいんですけども、せめて、せめてね、その人形から何かを考えて導き出してほしいと。私ども被爆者の気持ちを代弁してくださる人形だと思って、私は感謝しておりました」
◇ ◇ ◇
現代アート作家の菅 亮平さん。今後も「被爆再現人形」の研究を続けていくつもりです。

現代アート作家 菅 亮平さん(広島市立大学 芸術学部 講師)
「“実物資料” と“作りもの” のどちらかが優れている、劣っているということではなくて、どちらにもやはり果たす役割とその限界があるのだと思う。それをアートの専門家である私自身が問いたい」
原爆の悲惨さを“アート”でどう伝えていくのかー。人形は大きなヒントを与えてくれます。

 完全無料で広島情報
完全無料で広島情報






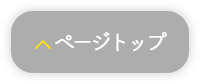




コメント (0)
IRAWアプリからコメントを書くことができます