今から140年前、広島県の世羅町に生まれた大妻コタカ。
明治・大正・昭和の時代に立ち向かい、
ただ一筋に女子教育の道を切り拓いた、その生涯をたどります。
第20話 思いがけない試練
昭和20年の東京大空襲は、大妻学院にも容赦なく襲いかかりました。
鉄筋コンクリートの新しい校舎は、3階以上に火の手があがり、敷地内にあった寄宿舎と、コタカさんの住まいは焼けてしまったのです。
それでも、犠牲者を一人も出さなかったことが、関東大震災を経験したコタカさんにとって、心の救いでした。
「建物は、またつくればいい」。
波乱万丈な60年の人生で、どんな苦難も乗り越えてきたコタカさんは、あきらめてはいませんでした。
そして迎えた、終戦の日。
日本に新しい時代の波がどっと押し寄せるなか、敗戦のショックから立ち直れない人々の先頭に立って、コタカさんは学校の再建に立ち上がりました。
何があっても自分のことを「お母さま」と慕ってくれる、生徒たちと一緒に前へ進もうと決めたのです。
その矢先、コタカさんのもとに思いがけない知らせが届きました。
戦時中、学校長でありながら婦人団体で奉仕活動を行っていたことが、教育者としての立場を超えて戦争に協力したとみなされ、連合国総司令部、GHQから「教職追放」の命令を受けたのです。他校の校長先生たちも、同様でした。
あまりのことに、言葉を失ったコタカさん。
その命令は、「学校への出入り(でいり)を一切禁止する」という厳しい内容でした。
空襲で自宅が焼けてからは、校長室に畳を敷いて寝起きをしていたので、そこもすぐに立ち退かなければなりません。
全財産を大妻学院のために差し出していたコタカさんには、貯金など一銭もあるはずはなく、着の身着のまま、寄宿舎の門番を務める職員の家に身を寄せたのです。
戦後になって、こんなカタチでいきなり希望を奪われるとは、思いもしなかったことでしょう。
そこから、コタカさんにとって、つらく寂しい日々が始まりました。
経済的な苦労はもとより、精神的な打撃が大きく、何よりも、わが子のように愛していた生徒たちに会えないことは、コタカさんの心にぽっかりと穴を開けてしまったのです。
世羅町の大先輩、大妻コタカさんの物語はいかがでしたか。
つづきは、また来週。
ごきげんよう。さいねい龍二でした。
▶番組ホームページはこちらをクリック「大妻コタカの生涯」を聞くこともできます。
この企画は、世羅町合併20周年と、世羅町出身の教育者で女性リーダーの草分け的存在・大妻コタカの生誕140年を機に、同氏の生涯を辿るオーディオコンテンツを制作、RCCラジオでシリーズ企画として放送するものです。
■ナレーター さいねい龍二
■ライター 角田雅子
■企画 奥土順二
■ディレクター・音効 石塚充
■プロデューサー 増田み生久
■協力 世羅町、大妻コタカ記念会、大妻女子大学
■写真提供 大妻コタカ記念会
 完全無料で広島情報
完全無料で広島情報









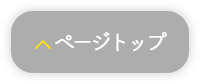




コメント (0)
IRAWアプリからコメントを書くことができます