今から140年前、広島県の世羅町に生まれた大妻コタカ。
明治・大正・昭和の時代に立ち向かい、
ただ一筋に女子教育の道を切り拓いた、その生涯をたどります。
第19話 戦時下に普及した五尺帯
昭和11年。
コタカさんが学校長を務める大妻学院にとって、華々しい出来事がありました。現在の千代田区三番町に、鉄筋コンクリートの新しい校舎が完成したのです。
地下1階、地上5階、6階建ての堂々たる建物で、エレベーターや空調設備などを備えた、最先端をゆく近代建築でした。
それは、亡き夫、大妻良馬さんの念願でもあり、コタカさんは喜びと同時に責任の大きさを感じていました。
新しい校舎に、生徒たちの希望に満ちた笑顔があふれていたころ、世の中には不穏な空気が漂い始めます。
昭和16年の12月、日本は太平洋戦争に突入しました。
当時、学校の校長先生たちは、社会教育にも大きな役割が求められ、コタカさんも婦人団体の役員や大蔵省の嘱託講師を頼まれていました。
戦時中には特に、服装の統制に関して、自らの経験をもとに研究を重ね、和服の改良を提案していたのです。
なかでも、コタカさんが考案した五尺帯(ごしゃくおび)は、戦時下の節約方法として普及しました。
帯の長さを通常の半分にして、材料費や縫製の費用を抑えたもので、畳んだり洗ったりする時間も節約できます。
そのうえ、着付けが簡単。体を強く締めつけることがなく、軽くて動きやすいという、いいことずくめの帯です。
この帯は大正時代、裁縫と手芸を教授するため宮家(みやけ)に上がっていたコタカさんが、夏の暑さ対策として生み出したものでした。
戦時中は、地方の講演会に行く寝台車の中でも、五尺帯で素早く身支度をしていたコタカさん。
その姿が、大日本女子社会教育会の会長、大橋広(おおはし・ひろ)さんの目にとまり、世間に紹介されたことで、「国策五尺帯」として広まったのです。
やがて、戦争が激しさを増すと、女性の服装はモンペ姿になりました。大妻学院の生徒たちもモンペを履いて、通いなれた学校ではなく、軍需工場へ動員されたのです。
世羅町の大先輩、大妻コタカさんの物語はいかがでしたか。
つづきは、また来週
ごきげんよう。さいねい龍二でした。
▶番組ホームページはこちらをクリック「大妻コタカの生涯」を聞くこともできます。
この企画は、世羅町合併20周年と、世羅町出身の教育者で女性リーダーの草分け的存在・大妻コタカの生誕140年を機に、同氏の生涯を辿るオーディオコンテンツを制作、RCCラジオでシリーズ企画として放送するものです。
■ナレーター さいねい龍二
■ライター 角田雅子
■企画 奥土順二
■ディレクター・音効 石塚充
■プロデューサー 増田み生久
■協力 世羅町、大妻コタカ記念会、大妻女子大学
■写真提供 大妻コタカ記念会
 完全無料で広島情報
完全無料で広島情報









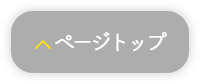




コメント (0)
IRAWアプリからコメントを書くことができます